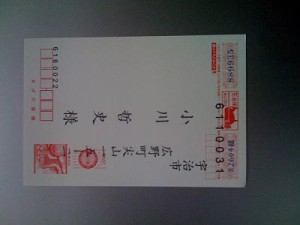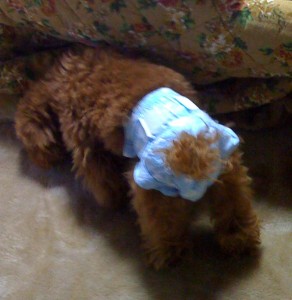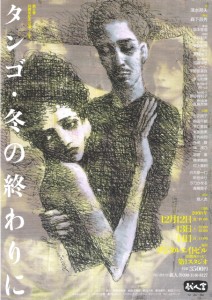健康・自然・家づくり「そよかぜの家ダイアリー」
外張り断熱の力を温度で比較
このところ寒い日が続いています。そんな時に限って事務所でのとりまとめ作業があって、ほぼ一日中事務所で過ごすことになってしまいました。普通事務所だと暖かくていいのかとお思いでしょうが、私の事務所は実家の一部屋を改造して作ったものなので、いわば田舎の大きな一軒家の一角です。
田舎の大きな家というと、とにかく寒いのです。ここで暮らしている私の母は、普段過ごしているLDKに大きな石油ストーブを置いて、朝一番にスイッチを入れます。それに何よりコタツがありますから、寒い中でも暖を取って過ごすことができます。
ところが、事務所にはもちろんコタツもありませんし、20年ほど前に取り付けたエアコンがあるだけです。あまりの寒さに、足もとにパネルヒーターを置いて、そこに足をのせて仕事をしています。もちろんジャンパーを脱ぐことはできません。
一方、私が住んでいる自宅はというと、5年前にそよかぜの家仕様で建築しています。だいたい20℃くらいをめどに暖房をしているのですが、21℃の事務所とは比較にならない暖かさです。暖房器具は、温水式のラジエーターが2台、ダイニングとキッチン部のみ床暖房が入っています。エアコンは冬場は使ったことがありません。輻射暖房ですから音もなく快適です。
まずは事務所、昨日の午後2時ごろ、エアコンの設定温度は21℃、運転が停止している状態です。このとき、エアコンのリモコンの高さに温度計を置くと、確かに21℃になっているのですが、床に置くとなんと15℃しかありません。立ち上がった時の頭の高さ(1.8m付近)は25℃もありました。運転を始めて6時間以上たつのに、足もとと頭とでは10℃も温度差があったのです。
一方自宅で今朝はかってみると、床に置いた温度計は19.5℃吹抜けの天井近くにおくとさすがに21℃、私自身が一番寒いと感じる暖房を何もしていない寝室の床付近でさえ、なんと19.5℃。家中の温度差がわずかに1.5℃しかありません。
上が一番高かった吹抜けの天井近く、下が寝室の床です。
防犯のための照明
年末にライトアップが各地で行われたのを受けて、癒しの照明についてコメントをしていました。キラキラと輝く電飾よりも、やわらかな電球色の光の方が日本の風景を美しく見せてくれるという考えが広まっています。色とりどりの電飾で飾られたライトアップもいいですが、嵐山の花燈篭のような落ち着きのある”あかり”が、日本の風景にはマッチするという考えが増えてきました。
先日ご紹介した景観配慮型の京都のコンビニも、外から見える照明を電球色を使用しています。
照明を青色にすると、犯罪が減るというものです。実際にJR西日本は、踏み切りの照明を青色にしているところがあり、飛び込み自殺の抑止につながったとしています。奈良県警も街灯を青色に変更することで犯罪が減らす効果があったとしています。
写真は宇治の天ケ瀬ダム。残念なことに自殺の名所でもあります。ここも昨年末に照明が取り替えられ、ごらんのように青色になったそうです。風景としては寒々しい感じなのですが、心理的には鎮静効果が高いのだそうです。
玄関は脳を安定させる
知って得する!ブリーズ・カンパニーの「建築医学」___karte1
”玄関は脳を安定させる”
正月早々ショッキングなタイトルですが、ブリーズ・カンパニーの2009年カレンダー「建築医学」の1月のコラムタイトルです。
以下転載
玄関は人の顔や脳にあたります。玄関が汚れていたり散らかった家で暮らしていると、脳が委縮する傾向があります。逆に、整理整頓・清潔を徹底し、広々とした印象にすることで、ストレスが緩和され安定した精神状態を保てます。狭い玄関には鏡を置くなどの工夫で、玄関に入った瞬間に「ホッ」とくつろげるような空間にしましょう。
こんな建築医学カレンダーが予備にとっておいたものが少しだけ残っています。
ご希望の方はメールにてお申し込みください。
七草粥
先程、お昼に七草粥を食べました。
正月の間に食べ過ぎ飲み過ぎで疲れた胃腸を助けてくれるのだとか・・・。
いわゆる春の七草が入っているのですが、最近では七草粥セットになって売っているそうです。特に癖もなく普通においしく食べられました。
ところで、春の七草ってどんなんやったっけ??というわけで調べてみました。
せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろなのだそうですが、何のことかわかりません。
すずな・すずしろはそれぞれ、かぶ・大根、せりはそのまませりですが、そのほかはいわゆる雑草のようです。けれども、枕草子の時代から正月7日に食べられていたというのですから、超ロングセラーメニューといったところです。
ちなみに、秋の七草は食べません。
日本郵便の力
正月早々珍しいものが届きました。
これでもちゃんと届けてくれる日本郵便はすごい!!
それにしても、投函された方は気づいていないのか??今度お会いした時にお話しします。
そういえば、最近年賀状のあて名書きを手書きで書かれる方はほとんどなくなりました。私の所に届いたものを数えてみても、1割もありませんでした。かくいう私もパソコンで宛名刷りしていますが、刷り終わってから宛名を確かめて、一言コメントを添えるようにしています。この方はずいぶん急いでおられたのでしょう。
ところで、この年賀状、普段通信のない遠方の友人などとの連絡は楽しみなものですが、ドカンとまとめて届くのでなかなかゆっくり読めませんし、誰からのコメントだったのかごちゃごちゃになってしまいそうです。また、喪中の方に出してしまったりということもありがちです。そんなことを考えてか、年末に挨拶状が何通か届きました。キリスト教の国ではクリスマスカードなのでしょうが、それもなじまないので、一年間のお礼と来年もよろしくという挨拶状という感じです。ドカンとくる年賀状に比べれば印象に残ります。喪中も気にしなくて済みますし、これから増えるかも知れません。そもそも、三ヶ日くらいは家でゆっくりしてというスタイルが全くなくなり、元旦からバーゲンに出かけるような時代ですから、年賀状のあり方も変わらざるを得ないでしょう。
私自身は、プライベートの年賀状は年末ぎりぎりに投函しましたが、会社としては今回出せませんでした。年賀状に代えて、早々のうちにニュースレター出すつもりです。松の内が過ぎたころに、ゆっくり読んでもらいたいと考えています。
新年のごあいさつ
新年明けましておめでとうございます。
昨年末に新しいページに移行し、新しい方にも見ていただけるようになり、ブログを書くのも力が入っていきました。今年はもっと面白おかしい内容を書いていくつもりですので、よろしくお願いいたします。
今日は、お正月気分で着物姿をアップしました。老け顔がより一層おっさん臭くなってしまいました。
私の実家のあたりでは、元旦にお寺と神社に年始のあいさつに行くのですが、去年から着物で行っています。(一張羅ですから毎年同じものですけど)着物を着て下駄を鳴らして歩いていると、何となく自分も日本男児だみたいな感じで、少し強くなったような気になります。けれども着なれない上に下駄では車も運転しにくいので、そそくさと着替えてしまいました。
氏神さんにお参りした後、家族で初詣に出かけました。
今年は、自宅の近くにある世界遺産、宇治上神社に行ってきました。
ここは、神社としては日本最古と言われ、本殿は平安時代に建立されたものだそうです。さすがに、元旦は大勢の参拝客で混雑していたので、建物をじっくり見る余裕もありませんでしたが、ひと通り見ても、それらしい古い建物は見当たりませんでした。
それもそのはず、写真の本殿は覆屋で、中に本殿が三つ並んでいるのだそうです。正月から調査不足でミスってしまいましたが、今度行った時にじっくり見てきます。
ともあれ、家族の健康と事業の発展を祈願して帰りました。
新年早々、ニュースではイスラエルの空爆やアメリカの崩壊が伝えられています。100年に一度どころではなく、人類が経験したことがないような激動の時代を迎えているのかもしれないと心配になりますが、何の不安もなく無邪気に遊んでいる子供たちを見ていると、「悩んでもしゃぁ~ないな」とも思えてきます。
自分自身と仲間を信じ、軸をぶらさず、頑張っていきたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
高断熱住宅に住み替えると医療費が減る!?
「安全な住環境に関する研究会」によると、08年、断熱性能の高い住宅に住み替えた101世帯343人を対象に、住み替え後の健康状態をヒアリングした結果、手足の冷えが解消する、せき、のどの痛み、喘息が改善するなど、体調の向上や病気発症の抑制が確認されたとのこと。
ただ、アレルギー性鼻炎などが住み替えを機に増加した症例もあり、もろ手をあげてということではなさそうです。やはりそこは「本物の健康住宅」でないといけません。
近畿地方の家の中の気温は日本中で一番寒いということを聞いたことがありますが、寒さをがまんすることで体調を崩すよりも、快適な空間で健康に暮らす方が、医療費が抑えられてお得ということです。
従来光熱費が安くなる分でイニシャルコストは取り返せますよというお話をしていましたが、医療費の分を計算すると、お得ということになりそうです。なにより、快適な毎日はお金で評価できませんけどね。
家庭用燃料電池が世界で初めて市販されるらしい
時々話題に上げていた、現在最も環境にやさしいとされている家庭用燃料電池システムが、いよいよ普及レベルになりそうです。
今年になって、東京電力や新日本石油がモニターを募集し、実証実験を行ってきたのですが、耐久性やコストの面でめどが立ったようです。折しも、一般のニュースでは電力価格の大幅値下げが報じられていますが、オール電化一辺倒に歯止めがかかりそうです。
写真は、新日本石油が現在使用しているもので、LPガス用と灯油用があります。市販レベルになると、都市ガス用がライナップに加わると思われます。
エネファームと名付けられたこのシステムは、燃料に含まれる水素と空気中の酸素とを化学反応させることで発電するので、窒素酸化物や硫黄酸化物の発生がほとんどない上、使用する場所で必要なだけ発電するので、余熱でお湯を沸かすこともでき、送電ロスもありませんので、トータルで高いエネルギー効率を達成するというものです。
夜は料金の安い電力会社の深夜電力を使い、昼間は自家発電を利用することで、ランニングコストはずいぶんと安くなるものと思われます。
あとは、コストの問題で、今までイニシャルコストが300万円くらいといわれていましたが、市販となるとどれくらいの価格になるのか注目するところです。特に、LPガスのエリアでは、オール電化切り替えに対抗する切り札みたいなものですから、イニシャルを抑えたリース方式などを出してくるんじゃないかと期待してます。
ただ、現在普及しているガスの発電システム(エコウィル)をみても、発電量が8KW/1日・1KW/1時間までに制約されており、これではメリットが半減します。電力会社との折衝でそのへんが緩くなるといいのですが・・・
クリスマス
今日はクリスマスです。クリスマスがキリストの誕生日だということはどれくらいの人が知っているのだろうか?
23日に子供が通う中学でクリスマス行事が行われ、キリスト生誕の演劇を見ました。この学校の生徒たちは少なくとも知っているでしょうが、ミッションスクールでない限り、学校で教えることはないでしょう。
ともあれ、2000年前に現れた救世主が、現代社会にも必要かもしれません。
 クリスマスとは関係ありませんが、「新型エスカレーター」ができたというのでご紹介します。
クリスマスとは関係ありませんが、「新型エスカレーター」ができたというのでご紹介します。
新型というからどんな形なのかとお思ったら、ご覧のように変わったのはベルトだけです。
ベルトに黄色い丸がプリントされていて、遠目に見ても、上りなのか下りなのかがはっきり見えるというものなのです。
「そんなんなくてもわかるやろー」という声が聞こえてきそうですが、これだけで事故防止につながるのだそうです。
そのうちに駅や商業施設で増えるかもしれません。
ドバイその後
ドバイでは建築ラッシュという話をご紹介したことがありますが、ついこの間まで、世界中の設計事務所やゼネコンがドバイに進出して、世界初・世界一のオンパレードでした。
私もぜひ一度この目で見てみたいと思っていたのですが・・・えらいことになっているみたいですね。
先日の報道ステーションでドバイの実態が報道されましたが、それによると既にバブルは崩壊しているようです。日本でも、リーマン関連の資本が凍結されたために、工事途中で止まったままのビルがあちこちにあるらしいんですが、ドバイでもこれと同じことが始まっているようです。
ところで、ドバイでは高さ1kmというような計画もあったように、超高層ビルが乱立しています。これが工事途中で中断ということになれば、解体しないといけないですね。でも、いったいどうやって解体するんでしょう?今まで解体が行われた高層ビルと言っても、100mにも満たないものしかありませんから、何百mもあるとどうやって解体するのか見当もつきません。まして巨額の解体費用をだれが出すのかと考えると、そのまま放ったらかしになりそうな気がしてなりません。
世界の話の中でめちゃめちゃローカルな話ですが、かつて琵琶湖沿いに幽霊ビルがありました。(数年前に解体されたと記憶していますが)ドバイが幽霊ビルが立ち並ぶ、文字通りのゴーストタウンにならないことを祈ります。
ライフスタイル別住むまち選び
これから家を持ちたいと考えたとき、住まいづくりの前にどこに住むかということを考えなければいけません。けれども、もともと生まれ育った土地を離れている場合、通勤が可能であれば360度どちらに行ってもかまわないということになり、友達が近くにいるとか、たまたま広告を見たりして、分譲住宅を買うという行動に移りがちです。
分譲業者もその辺を考え、小規模の開発ではなく、街並みをデザインするという形で開発をしていることが多いのですが、数千世帯というレベルの開発をしないと、まち全体をデザインすることは無理でしょうし、そうなると何十年もかかってしまい、その先には現在千里ニュータウンなどが抱えるまちのゴーストタウン化が心配されます。
ということは、今現在できている町並みをみて自分に合うところを選ぶ方が安心なわけですが、それを自分の足で探すというのは大変な労力が必要です。不動産屋さんに行って相談しても、どのエリアと希望を言うことができず、勧められるままにことが運んでしまいます。
そんな悩みを解決してくれるかもしれない新しいシステムができました。
賃貸物件の検索サイト「CHINTAI」が、ライフスタイル別の土地探しということを始めました。
ご覧のような画面で、コミュニケーション・趣味・街のイメージなどを選んでいきます。もちろん従来の希望沿線や通勤時間なども考慮して、ネットで検索をしてくれます。そして、検索結果がこのように表示されます。
マッチ度が%で表示され、街の特徴も見やすく表示されています。
まあどれほど正確にあわらしているかは別として、切り口は面白いと思います。今のところ首都圏だけしか対応していませんが、今後の展開に注目したいと思います。
景観配慮型コンビニ
京都に景観条例が導入され1年余りがたちましたが、街の必需品(?)となったコンビニにも変化が見られます。
ちょっと前に、祇園八坂神社前のローソンが看板を一新し、店内の照明も電球色に替え、景観配慮型店舗として生まれ変わりました。
ご覧のように、格子を付けて京都らしさを演出し、看板も定番のブルーを使用せず、ちょっと見たところローソンとわからないくらいです。ちょうど、昨晩忘年会が円山であったので前を通りましたが、店からこぼれる明かりが少し黄色っぽくなって、周りとなじんでいました。ただ、ちょっと照明が明るすぎるとは感じましたが・・・。
一方、最大手のセブンイレブンも、上賀茂に環境配慮型店第1号を出店しました。
こちらは、独立店舗ですが、照明にLEDを使用したりすることで、CO2排出量を従来よりも減らしたのだそうですが、デザイン的には屋根をこう配屋根にしたぐらいで、どこから見てもセブンイレブンですし、あまり京都らしいとは思えません。
京都ではマクドナルドもロゴマークの色を変えていたりしますが、行政の指導もあるでしょうが、企業の姿勢・センスが問われるところでしょう。それが売上と結びつくかどうかはわかりませんが、今更定番の看板を使用しなくても、店名は十分に浸透していると思うので、センスの良さを競ってほしいものです。
電気温水器の訪問販売に注意
国民生活センターが、電気温水器の訪問販売に関してもんだいが急増しているとして注意を喚起しています。
センターによると、消費者から「よく考えると高額だった」「急がされて契約してしまった」などの相談が多く寄せられ、今年度は上半期ですでに688件もの相談が寄せられているそうです。
テレビでも「オール電化にするとこんなにお得!」という内容のものがよく流れていますが、それぞれのライフスタイルによって、電気・ガス・石油を使い分けた方が得な場合も多いのです。単純に考えれば、電力会社・電気工事店などが、オール電化工事を勧め、ガス会社はそれに歯止めをかけるという構図が浮かび上がります。一般の消費者の方が、双方の意見を聞いて的確に判断することはなかなか難しいことですから、中立的な立場の工務店や設計事務所に相談するのが良いでしょう。
お湯を沸かしたり調理をしたりして消費するエネルギーは、確かに電気の方が安いことが多いのですが、冷暖房費についてよく検証することが必要です。特に暖房時期に大きな差が出てきますので、暖房機器の選定とあわせて検討しなければいけませんし、その住宅の断熱性能も配慮しなければいけません。また、当初の費用やランニングコストだけでなく、機器類の更新(老朽化による取替)のコストも考える必要があります。
脅かしているわけではなく、なかなか高度な判断が要求されますので、慎重に考えましょう。
鴨鍋
冬は鍋がいいですね。我が家では最近小5の次男が鍋にはまっていて、「毎日でもええで」と言っています。妻も準備が楽だそうで、よく鍋をします。と言っても、全員そろわないとできませんから、昨日は久しぶりの鍋となりました。
 鍋にもいろいろありますが、冬季限定(そもそも鍋は冬か?)食材で脂ののった鴨がうまいんです。京鴨というブランド鴨もあるようですが、我が家では毎年、私の友人の鶏肉屋さんで、安くておいしい鴨肉を分けてもらいます。昨日は今シーズン初の鴨鍋でした。
鍋にもいろいろありますが、冬季限定(そもそも鍋は冬か?)食材で脂ののった鴨がうまいんです。京鴨というブランド鴨もあるようですが、我が家では毎年、私の友人の鶏肉屋さんで、安くておいしい鴨肉を分けてもらいます。昨日は今シーズン初の鴨鍋でした。
我が家のレシピは、厚めに切った鴨肉のほか、具材は長ネギ・水菜・シイタケ・豆腐だけ。昆布だしをしっかりとって、薄口醤油と塩で味を整え、あとは炊くだけ。鴨肉はしっかり火を通しても固くなりません。水菜はハリハリ鍋の要領で茎の部分だけを使う方が良いのですが、きのうはご近所でいただいたものがあったので葉っぱごと入れました。
今回は、脂身の多いところや堅そうなところをフードプロセッサーにかけて、鴨団子も作ってみたところ(もちろん妻がですが)、なかなかおいしかったです。
写真で鴨肉1kg。昨日はおばあちゃんも呼んで、5人で完食です。安くておいしい我が家の定番料理でした。
芝居を見てきました
昨晩大学時代の友達のすすめで、演劇を見てきました。
こういう”お芝居”というものを見たのは、はずかしながら初めてでした。その友人もチョイ役で出るというので、同級生3人で見たのですが、3人とも初体験でした。
皆さんプロの役者さんということで、素人目に見ても芝居の完成度は高かったように思います。というか、高校時代の文化祭や、子供の演劇くらいしか見たことがないもんで・・・。内容的には何とも難しい・・・、2時間はあっという間に過ぎ、一遍見直したいような気になりました。一度だけでは私には理解できなかったのですが、何か引き込まれるような魅力はありました。また機会があれば行ってみようと思います。
芝居の後は、久しぶりに同級生3人でゆっくりと飲みながら話をしました。40を過ぎ、みなそれぞれにいろいろなことを経験し、学生時代とはまた違う刺激があり、話は尽きることがありませんでした。とても楽しい一夜でした。
RSSサイト
友人がRSSリーダーのことをブログに書いていたので、私もさっそくアイフォンで使えるように設定をしました。
彼はその道のプロですから簡単にできるのでしょうが、私は結構手こずってしまいました。
なんやかんやトやっちるうちに、ブラウザーでも同じような機能ことができることを発見しました。
まず、そよかぜの家のトップページを開いて、インタネットエクスプローラの右上のフィードというボタンをクリックすると、
下のような画面が現れます。
 次に「このフィードを購入する」をクリックするとできあがり。「購入する」と書いてありますが、費用はかかりませんのでご安心ください。
次に「このフィードを購入する」をクリックするとできあがり。「購入する」と書いてありますが、費用はかかりませんのでご安心ください。
こうしておけば、いちいちぺーじをのぞいて更新しているかどうかを確かめなくても、下の画面で確かめられます。
お気に入りボタン→フィードボタンを押すと、下のような表示になり、更新があるとタイトルの横に(1)のように表示されます。
そのタイトルをクリックすると、更新内容がテキストで確認できます。
私は、友人お勧めのPDAで更新をチェックしますが、家のパソコンで見ている方は、これの方が使いやすいと思います。
おためしあれ。
CDでもDVDでもありませんよ
先日いつもお世話になっている方々に、そよかぜニュースと2009カレンダーを送付いたしました。
ここ数日、「この間ありがとう」と声をかけていただくのですが、どうもカレンダーをCDやDVDと勘違いしておられる方が多いようです。実は、出来上がってきたときに子供に見せたところ、どうやって使うのかが分からなかったんです。つくっている方は、卓上カレンダーとしてはじめからつくってますから、当たり前のように組立(というほどでもありませんが)するのですが、「これ何?」と初めて触る人には、ちょっと不親切なものになってしまいました。そこで、そよかぜニュースには、使用している形を写真に撮って挿入していたのですが、そこまで読まれていない様子です。
ニュースレターを出すとき、はたしてどのくらいの人が読んでくださるのか気になるところですが、意外なところで実態が判明してしまったのです。まあ、時間のある時にゆっくり読もうと思っていただいている方もあるようですので、あまり悲観はしていませんが、友達から手紙が届いたらすぐに読むわけですから、すぐ読みたくなるように内容をもっと工夫しなくてはいけないですね。
さて、その「建築医学」カレンダーですが、けっこう反響がきています。内容的に真新しいものなので、初めて聞かれる方がほとんどだと思います。また、ショールームの写真もテーマに合わせて挿入していますから、イメージしやすいとのこと。
若干予備が残っていますので、もう1個欲しいという方はご遠慮なく。早いもの勝ちです。
京都でエレベータ事故
昨日京都市内でエレベータの事故がありました。
扉が開いたままカゴが降下し、エレベータの天井と廊下の床の間に足を挟まれたといいます。めっちゃいたそうですね。
今回の事故はマスコミでも大きく報道されていますが、知らないところで小さな事故はいっぱい起きています。たとえば、エレベータが止まって閉じ込められたなんていう話は実によくあります。
もともと、エレベーターは製造メーカーが設置~アフターメンテナンスまでをトータルでやっていた業界でした。ところが、数年前規制緩和といって、メンテナンス専門の会社が参入するようになりまして、ややこしくなってきたのです。今回も業務上過失というふうに報じられていますが、メンテナンス会社が過失を問われるのか、製造したメーカー・設置した工事会社かなど、複雑になる恐れがあります。
このエレベータが設置されたのは1988年だそうで、まる20年たっています。いったいエレベータの寿命ってどれくらいなのでしょうか。
一般に言われているのは20~30年で、メンテナンス状況によってもかわるし、いわゆる”あたり・はずれ”もあるのだそうです。
今回のエレベータも故障の兆候はあったようですし、リニューアルが必要な時期だったのかもしれません。
最近、「古くなったファンヒーターを引き取ります」という広告をよく目にします。製造メーカーとしてとことん責任を取ろうという姿勢であり、素晴らしいことだと思いますが、はたしてそれが正しいのでしょうか?企業にそれだけの余力があれば対応できますが、そんな時代でもありませんから、われわれ使う立場の方も、自分の目で安全を確かめることが必要なのではないでしょうか。
尖山ショールームをgooglemapに登録
そよかぜの家の尖山ショールームを、googlemapに登録しました。
「そよかぜの家」で検索すると出てきます。ストリートビューで表からも裏からも見ることもできます。
ショールームは事前予約が必要です。何と言ってもふだん私が住んでいる家なので、お客さんがお見えになる前に少しは片づけないと・・・。
自宅をショールームに開放するメリットは、何よりも自分自身が住んでいますから、住み心地・使い勝手を実体験でお伝えできることです。大きな吹抜けの開放的な空間にすると、実際はものすごく空調費がかかるとか心配されますよね。そんな疑問にも、ズバリお答えできます。そして、そよかぜの家の性能を最大限引き出すために、自らがモニターとなって工夫を重ねていますから、住み方まで突っ込んだフォローが可能なのです。
今なら、薪ストーブの暖かさ・なんともいえないやさしさも体感できます。ぜひこの季節に。
ストーブ薪の樹種による違い
昨日はかなりの冷え込みでした。尖り山ショールームも一日中薪ストーブを焚いていました。
今日は、ストーブ用の薪の種類についてご紹介しましょう。
ストーブ用薪には広葉樹を使いましょうという話は何度かしているかと思いますので、その先の話を。
広葉樹といっても種類はいっぱいあります。薪として流通しているもので一番多いのはおそらく、クヌギ・ナラなどでしょう。インターネット通販ではだいたい1束(6~8kg)あたり500円前後で売られています。ちょっと高級な薪ということで、サクラ・カシ・ケヤキなどがあります。これらは流通量も格段に少なく、価格も1束あたり600~800円もします。
それではこの価格の違いは何なのかをご説明します。
もっとも大きな理由は火持ちの違いです。ちょうど昨日は去年買った1束600円カシの太薪と今年買った1束400円の広葉樹ミックス薪を比べてみました。
カシの薪は極太なので、1束に3本くらいしか入っていませんがその力は強大です。2本の極太薪を午後1時ころ放り込んで火を小さく絞った状態で外出し、夕方5時ごろ帰宅するとまだかすかに火が残っていました。もちろん家の中はポカポカです。燃費を計算すると、600÷3×2 ÷ 4 = 100円/時間 ということになります。
一方、帰宅後、カシの薪がなくなったので、広葉樹ミックス(こちらは細い目で1束に7~8本入っています)を4本投入。こちらは1時間おきぐらいに薪を足してやらないといけないので、最後に投入した11時までに、2束使いました。おそらく深夜1時ごろまでは火が残っていたと思いますので、それで燃費を計算すると、400×2 ÷ 8 = 100円/時間 ということで、カシと同じくらいになりました。
燃費は同じなのですが、カシの場合、2~3時間ごとに薪を足すだけなので、手間がかからないというメリットがあります。単に薪を入れるということだけでなく、その前段階で薪を倉庫から運んでくることを伴いますから、ヘビーユーザーにとっては大変ありがたいということになるのです。
ただ、欠点として火が付きにくいということがあります。その点広葉樹ミックスはすぐに火が点きます。焚き付けの時には、広葉樹ミックス(私は針葉樹も使います)、火が安定したらカシという使い分けがベストかもしれません。ナラやクヌギについても、カシに比べると火持ちはだいぶ劣りますがその分火点きはいいといえます。要は燃費に応じて価格が決まっていると考えてよいと思います。
週末だけとか、夜だけ使うという方なら、広葉樹ミックスなどの安価な薪で充分だと思いますが、一日中使うという方は、カシの極太を試してみてはいかがですか?
ちなみに、私がここ数年購入している薪屋さんは、今シーズン分は完売のようです。極太薪を手に入れるのはなかなか難しいので、来年早めに段取りしてみてください。
おしゃれな暖房・・・
今日はこの冬一番の冷え込みになりました。宇治市では最低気温が―3℃まで下がったそうです。
この季節暖房は当然欠かせません。いくら高性能な家だといっても、暖房なしというわけにはいきませんが、せっかくおしゃれな空間を作ったのに、ファンヒーターや石油ストーブなどを置いては台無しです。また、エアコンの暖房は乾燥した空気をかき回すので、あまり快適とは言えません。
そよかぜの家でお勧めしているのは輻射暖房です。焚き火に当たったり太陽の光を受けると温かいですね。これが輻射熱です。空気を暖めるエアコンやファンヒータと違って、直接体が熱を受け取るので、周りの空気が冷たくても体は暖かいというわけです。
住宅における輻射暖房器具といえば、デロンギヒーターなどでおなじみのパネルラジエーター(オイルヒーター)です。ちょっとレトロな感じがして、デザイン的にも悪くはないと思いますが、電気代が高くつくという欠点があります。
理想的なのは床暖房。これも、温水式・ヒーター式・蓄熱式などに大別されるがそれぞれに特長があり、用途に合わせて使い分けます。家全体を暖めるという用途で考えた場合、温水式が最も効率的でしかも快適だと私は考えています。
この床暖房、残念ながら当社のように分厚いムクのフローリングの場合は使えません。フローリング自体が熱を伝えにくいので、輻射熱が半減してしまうのです。
そこで、写真のように、ダイニング・キッチン部分の床をタイル張りにして、ここに床暖房を仕込むことをよくやります。けれども、これだけの面積の床暖房で家全体を暖めることは不可能ですから、他の暖房が必要です。実は写真中央に見える白いパイプが、温水ラジエーターなのです。今回はガスの給湯暖房システムを採用しましたが、高機能の給湯機(エコジョーズというやつです)を利用すれば、給湯機1台で、床暖2か所、ラジエーター2か所に加え、浴室のミストサウナまでまかなえてしますます。もちろん給湯もします。冬場のガス代は結構かかりますが、電気や灯油などを使わない分トータルではそれほど高くはないと思います。
ランニングコストだけを考えると、オール電化が得な場合もありますが、同じシステムを電気でやろうとすると、イニシャルコスト・メンテナンスコストともに、かなり高額になり、ライフサイクルコストとして考えた場合、ガスのほうが得だという判断をしました。
おしゃれさを追求すると、PSヒーターも魅力的ですが、予算は重要なファクターですので・・・・
大阪ガスさんももう少しバリエーションを増やしてくれるといいのですがね。