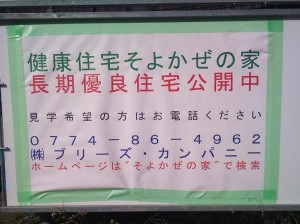知り合いの紹介でこんな相談を受けました。
「基礎にひび割れが入っていて気になる。ひび割れから水がしみ出てくる」とのこと。
3年ほど前に分譲を購入されたのですが、当時販売していた会社はすでになくなっていて、どこに相談してよいかわからず、私の知り合いにどこか知らないかということになったようです。
さっそく現場を見に行ってみると、

こんな状態。
これはベタ基礎のうち継部分から水がしみ出たものであることは一目瞭然です。おそらく床下一面に水がたまっているはずです。
ではどうして床下に水がたまったのかということになります。
まず考えられるのは給水・給湯からの漏水。この場合、わずかずつでも常時水道メーターが動いているはず・・・
メータをみると全く動いている様子がない。
では排水か?2階の水回りの位置をチェック。同時に一階の天井に濡れはないかチェック。いずれも大丈夫。そもそも排水だと臭いもあるはずだが、臭いはない。
これは床下にもぐってみるしかないな、ということになりましたが、点検口などがないので、で直すことに。
日をあらためて、点検口を設置するために大工さんを、床下の配管をチェックするために水道屋さんを連れて、お伺いしました。

怪しいとにらんだトイレの横に押入れがあったので、そこの床に点検口をつくりました。
すると、ご覧の通り、プール状態。5cmくらい水がたまっていました。
水道工はさすがに目ざとく漏水個所をトイレの給水管に違いないと予測しました。わずかな水漏れの音を聞き分けたそうです。
原因は推測できたものの、水を抜かないとどうしようもないということで、

影響の少なそうなところを選んで、基礎に穴をあけ、水を排出することにしました。
写真のように、トクトクと水は流れてきますが、床下一面にたまった水の量は半端ではありません。水位は一向に下がりません。
仕方なく、強硬突破!
勇敢な水道工は、カッパに身を包み、探検隊のように水にぬれながら、床下の奥にもぐっていってくれました。

これはトイレ床下の土台。びっしょり濡れてしまっています。
この土台の真上に部分で、給水の立上り管から水が漏れていたようです。
床下で、立上り管を切断し、あらためて床給水の配管をして完了。
基礎に開けた穴は、水がすっかり抜けてからふさぎに行きました。
ところで、今回は水が漏れていたにもかかわらず、水道メーターは全く動いていませんでした。水道料金も特に高くはありませんでした。
水漏れの量が、ごくわずかであったために、水漏れに気付かなかったということになります。
それでも、数年をかけて床下一面にたまった水は、おそらく2tくらいでしょう。洩れでた分を合わせると、もっとたくさんの水道代を余分に払っていたことになります。
それでも建物に影響が及ぶ前に見つかってよかったですね。